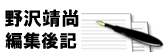|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
昨年の1月1日に引き続き、今年の元旦もまた、都内の空手道場にて一人稽古をさせていただいた。終了後、ストレッチをながら、道場主の先生と会話をしていたところ、先生から「野沢さん、腕が太くなりましたね、前腕が」と指摘された。 |
|
私の愛用するコンピュータは、パワーブック160である。 |
| ←前へ |
| パワーのある人は、本当に存在する。 この「パワー」とは、物を持ち上げる力や技の威力などではない。周囲の人間に強烈な影響を与え、突き動かしてしまう力のことであり、影響力とでも言おうか。それも適切な表現ではないので、仮に「パワー」としておく。 パワーのある人…、決定的なところではブルース・リーだ。ブルース・リーを見たことによって、人生が変わった人間が、世界中にどれほどいることか。最近でも、『トランスポーター』の監督ルイ・レテリエが、「ブルース・リーの影響を受けなかったアクション映画なんて、存在しない」と嬉しい断言をしてくれているように、そのパワーは今なお継続中である。 アンディ・フグが亡くなったとき、その報道や回顧特集などで、私たちは、走り回された。亡くなった人間が、これほど多くの人たちを動かすことに、アンディという人のパワーを感じずにいられなかった。「死せるアンディ、生ける編集者を走らす」と追悼号の編集後記に書いたくらいだ。 そして、緑健児氏である。この人は、怖い人だ。この「怖い」という表現は、「おっかない」といった意味でも、「不気味」といった意味でもない。 その全身から発せられる無言の厳格さが、叱咤としてこちらに伝わってしまうという点から、私は怖いと感じてしまうのだ。 第5回世界大会で表彰台に立った緑氏の姿を見て、「あの人は世界でいちばん努力して優勝したのに、お前はいったいどれほど努力しているのだ?」と思えてしまい、緑氏が何か言ったわけではないのだが、怒られているような思いを勝手に抱いてしまっていた。 今回の取材に当たって、緑氏は実に気さくに、全面的な協力をしてくれた。そんな人に「怖い」という表現を使ってしまっては、はなはだ失礼なのだろうが、それでも「怖い」くらいのパワーはまったく衰えていなかった。 取材当日は氷雨が降り、取材の翌日も非常に寒い日となった。私は、こんな日に、朝からウェイトなんてやりたくない、休んでしまおうか、と布団の中でグズグズしていたのだが、ふと「緑さんなら、どうする?」との考えがよぎる。その瞬間、飛び起きてしまった。 普段なら、なかなか布団から出ることのできない冬の朝に、人一人、飛び起きさせてしまうのだから、これはたいへんな影響力だ。しかも、その日は、いくつかの種目で新記録まで出てしまった。 話は前後するが、緑氏は取材を終えると、道着の上着を脱いで、腕立て伏せを始めた。その隆起した肩と胸に圧倒された私は、思わず「今もウェイトは続けているんですか?」と愚問を発してしまった。一瞬、しまったと思っている私に対し、緑氏は、穏やかな口調で「ほんの少し」と答えてくれた。 「ほんの少し」…。この人の「ほんの少し」がいったいどれほどになるのか。想像するだけでも気が遠くなってくる。 緑氏のおかげで、ウェイトの記録が伸びた私だが、それはあくまで、ほんの少しだ。 それも、一般的な意味でのほんの少しである。 |
| ←前へ |
| 八極拳の歩法訓練で、呼吸をしっかり意識して動作を行うようにした。具体的に述べてもわかりにくいとは思うが、一つ例をあげると、前手前足を引き、蓄勢となりながら息を吸い、そこから真下へ落として息を吐き、前へ足を大きく踏み込みながら息を吸い、踏み込みの足が着地する瞬間に、息を吐いて突く、といった具合だ。 息を肺活量いっぱいの許容限度まで吸い込むので、自然と動作は大きく、遅くなる。その間は、姿勢を保たねばならず、倉本成春師範のいわれる停止筋肉的な身体操作が要求される。また、震脚や打ち込みが、予想以上に強化されるので、腕の勢いを止めるための肩、床へ着地する衝撃に抵抗するための下半身の筋肉が動員される。 実は、呼吸を意識して行うことにより、筋肉自体への負荷は、はるかに大きくなる。 それゆえ、訓練を続けていくうちに、よけいな力が入る余地がなくなり、筋肉への意識が薄らいでいく。力を入れていては続けることができず、自然と脱力した状態になっていくのだ。 頚、腕、肩、胸、背、腹、腰、大腿、下腿といった肉体の各部位を動かそうという感じではなくなり、まず呼吸が先にあり、呼吸をしていれば、肉体がそれに応じて動いてくれる、という感じになる。 いにしえの達人が、呼吸を行っていれば、強さも身につく、といった意味のことを語っていたのは、こういう現象を踏まえたものだったのかもしれない。事実、脱力した状態で呼吸を続けていく限り、動作は続けられ、その上、息が乱れることがない。 この歩行訓練は、通常の回数を終えると、汗が滝のように流れ、息も絶え絶えになる。しかし、今回は動いていて気持ちが良いくらいで、すべての動作を終了した直後、もう一度最初から繰り返せるな、と本気で思え、生徒に「もう一回やろうか?」と口走ってしまい、ギョッとされたほどである。 練習を続けて長い年月がすぎると、日に日に上達する、などという成果は見られなくなる。しかし、年に数回、突然、目の前が開けるような感覚をおぼえることがある。 今回は、呼吸だった。何かをつかめた、と思えるのは、そんなときだ。これこそ、醍醐味というものだろう。 私は、「練習をするのは、練習後にうまいビールを呑むためだ」と公言してはばからない。映画『AIKI アイキ』で、主人公が先生に、「どうしたら先生みたいに強くなれるんですか?」と尋ね、先生がにっこりとうなずいて「それはね、私のようにたくさんビールを飲むことです」と答えるシーンには(実はその後に先生の名言が続くのであるが)、他人事(ひとごと)ならぬ共感を、強烈に抱いてしまったくらいだ。 練習してビール。その快感すら及ばない醍醐味があるからこそ、一生の業となり得るのだろう。こんなことを書くと、私を知る人から「何を偉そうに。呑むためだけに やってる奴が…」と思われるに違いないが、これほどの経験を味わってしまうと、言葉にせずにはいられなくなるのが人情というものでしょう。 |
| ←前へ |
| 私と互いに「腐れ縁」と認め合う巨椋修(おぐら・おさむ)氏が、このたび「不登校の真実」というセミドキュメンタリーを完成させた。 漫画やイラストに始まり、小説や研究本の執筆へ。さらには、陽明門護身拳法という格闘技団体を作り、そしてとうとう映像の世界へと踏み込んでしまった巨椋氏のエネルギーと情熱は、恐れ入ったものがある。 観客の一員になるくらいしか、私に協力できる場面はなさそうなので、上映会場には、ぜひ駆けつけたいと考えている。 巨椋氏には、何の責任もないことなのだが、私がどうしても許せないことは、この作品が「映画」として、新聞などで紹介されていることなのだ。 巨椋氏も認めているように、フィルムを使った撮影は、莫大な予算がかかるため、ビデオによる撮影を行い、コンピュータを使って編集をし、予算を抑えたという。 それはそれで、まったく正しい。だが、そうした完成された映像は、映画では決してない。ビデオ作品である。 映画とビデオは、まったく違う。新宿ピカデリーで上映された『ハリー・ポッターと秘密の部屋』と、ビデオやDVDとやらで発売された『ハリー・ポッターと秘密の部屋』とでは、同じ魔法使いの少年が大活躍しようと、まったく違ったものを見たことになってしまう。 映画とビデオの違いを説明し始めたら、きりがないが、端的に述べるなら、光源体の光を受けて輝く月と、みずからが光源体となって輝きを放つ太陽の違い、となろうか。そう、映画とビデオは、月と太陽ほどの違いがあるのだ。 にもかかわらず、世間は、フィルムでなく、ビデオで撮影された映像を、無責任に「映画」と呼び放つ。そうした風潮に追い撃ちをかけるように、映画がデジタル撮影され、映写や世界への配信がデジタルで行われることが、映画の革命といった感じで歓迎されるような説が飛び交っている。 しかし、フィルムで撮影されず、フィルムからスクリーンへ投影されることがなくなったら、それはもはや映画ではなくなる。 画質の向上や予算の削減など、デジタル化の利点は多かろう。しかし、『スター・ウォーズ エピソード3』が、高密度なデジタル映像で完成され、通信で映像が配信され、液晶プロジェクター設置のシネマコンプレックスで上映されるとしたら、そんなものを見に行こうとは思わないだろう。 『スター・ウォーズ エピソード3』を極上の画質で見るよりも、退色した赤くなってしまったプリントで、成瀬巳喜男の『ひき逃げ』を見る方を私は選ぶ。 『スター・ウォーズ エピソード3』どころか、いずれはすべての映画がデジタルになる、そしたら、お前の言う「映画」なんか、見れなくなるんだぞ、と言われることだろう。 それでいい、と私は答える。フィルムさえなくなるようなら、自宅に映写設備を置き、『忠次旅日記』のフィルムを手に入れて、毎日でも見てやろう。新作を液晶画面なんかで見るより、その方がずっと楽しいではないか。 『丹下左膳 第1篇』がイギリスで見つかったというのなら、『新版大岡政談』を、世界の果てまで探していこうじゃないか。 なるほど、希望のない未来に目を向けるより、失われたとされる過去を振り返ればいい。視界がとたんに開けた気分だ。 |
| ←前へ |
| 今、編集部内では、なぜか第5回大会が流行っている。正確に記すと、極真会館主催の第5回オープントーナメント全日本空手道選手権大会のことである。 どういう経緯でこういうことになってしまったのか、あまり記憶が定かではないのだが、BUDO−RA第4号で盧山初雄館長の特集を組むに当たり、昔のビデオを見直したりしていたからだろうか? この大会は、本当に何度でも見入ってしまう。盧山館長や山崎照朝先生の姿はもちろん、中村忠・現誠道塾会長、大山茂・現ワールド大山空手総主、二宮城光・現円心会館館長、富樫宜資・現無門会会長…。本誌でもおなじみの先生方が、生き生きと動いているところが最大の魅力だろうか。 もちろん、空手技術の面でも、今月号で、真樹日佐夫先生と盧山館長という時の証人が語ってくれているように、この大会は、勉強になるところが非常に大きい。 これは、うちの編集部ならではのことだろうが、山田編集長と、決勝戦を再現してみよう、ということになった。 山田編集長が山崎照朝先生、私が盧山館長となる。左の掌底で入り、右の逆突き、という試合通りの順序で攻撃すると、これがおもしろいように決まる。 山崎先生は、右の下段を蹴って、あるいはスイッチして左上段廻し蹴りを蹴ってくるのだが、そこに合わせて前進しながら掌底を打ち上げると、カウンターとなり、山崎先生側の動きが封じられてしまう。 そして、三日月蹴り。これは、いきなり出しても入る。山崎先生の構えは、左手を大きく上に上げているから中段が空いている、といってしまえば、それだけなのかもしれないが、山田編集長によると、後屈立ちの構えから蹴ってこられると、距離感が狂ってしまう、ということだった。 その他にも、いろいろ発見なり研究なりができ、成果は大きかった。物真似ということではなく、真剣に動きを模して組手をしてみると、見ているだけではわからなかったことが体で理解できるようになってくる。いずれは他の人の動きでも試してみたいものだ。 真樹先生との対談で、盧山館長にお会いして数日後、山崎照朝先生にもお会いする ことができた。第5回大会ビデオをきっかけに、円環の動きが一九七〇年代にも拡がっているのだろうか。 思えば、世間全体も七〇年代に回帰といった風潮がある。その時代に育った世代が、各媒体での発言力を持つ時代となった、ということもあろうか。 しかし、単なる回顧にしてしまってはいけない。常に現代と連動させながら、円周を七〇年代にも拡げていけばいい。 今月登場していただいた真樹先生にしても、盧山館長にしても、永遠の青春を主張し、実際にその通りの行動を見せてくれている。 過去や回顧といったとらえ方でなく、あらゆる時代を常に更新される現在としてとらえていけば、古くなる、といった概念は消える。 第5回大会は古い大会ではない。盧山館長の戦法は古い戦いではない。真樹先生の作品が古い文章ではない。ブルース・リーは古い人ではない。『忠次旅日記』が古い映画では決してない、と断言したい。 |
| ←前へ |
|
空手道場は「いい場所だなあ」と思える立地のところが多い。例えば、駅に近い、繁華街の中心、住宅街の中心、人通りが多い、学校に近い、などなど。 |
| ←前へ |
|
夏休みはどうでしたか? |
| ←前へ |
|
中村頼永氏、関誠氏のご尽力により、香港映画『中泰拳壇生死戦』を見せていただいた。 |
| ←前へ |
|
祖母の三回忌にあたり、一年ぶりに帰郷した。 |
| ←前へ |
|
十月に、「ジョー&飛雄馬」の刊行が終了した。 |
| ←前へ |
|
「緑健児が教える ビギナー君の黒帯チャレンジ」の取材は、熱血肌の緑健児代表だけに、指導に熱が入ってくる。横で取材をしながらも、中島君を応援したくなってきて、こっちまで力が入ってしまう。 |
| ←前へ |
|
BUDO−RA無法地帯の対談で、先月、名画座のことが話題になった。懐かしくなったので、思い出の名画座を振り返ってみたい。 |
| ←前へ |
|
宮本武蔵を真似るわけではないが、「我、事において後悔せず」という人生を送っていた。しかし、つい先日、珍しく後悔の念を抱かされてしまった。 |
| ←前へ |
|
靭帯物語その一 |
| ←前へ |
|
靭帯物語その二 |
| ←前へ |
|
靭帯物語その三 |
| ←前へ |
|
靭帯物語その四 |
| ←前へ |
|
靭帯物語その五(最終回) |
| ←前へ |
| 靭帯物語延長戦 切れた靭帯は元通りにならないのだが、膝は順調に回復し、日常の歩行はもちろん、特定の手技(アッパー系統)は、こなせるようになってきた6月の後半、朝起きたら、靭帯を切った方ではない、右膝に痛みをおぼえた。 膝の裏側が強烈に痛む。前の晩、酔っ払って転んだのか? この程度なら3日もあれば治るだろう、と放っておいたが、一向に痛みがひかない。それどころか、痛みが増し、どんどん腫れてくる。ついには、足を地面に着くことができなくなってしまった。 観念して医者へ行く。また、MRI検査だ。しかし、異常なし。どのような動作で傷めたのか、と医者に尋ねられても、記憶がないので答えることができない。泥酔して転んだとばかり思っていたが、擦り傷などの外傷がまったくないので、転んだにしては、おかしい気もしてきた。 リウマチ、偽通風、細菌感染など、さまざまな可能性を想定して、他にもいくつか検査を行うが、結局、原因がわからない。それでも毎日、膝が大腿よりも太く腫れて、病院で関節液を抜いてもらう。その繰り返しだ。一本ではあるが、松葉杖生活に戻ってしまった。 倉本成春先生が心配してくださり、取材ではなく療法院へ伺う。抗生物質で強引に腫れを抑え、その上で鍼や灸を施していただいた。鍼灸の即効性は絶大で、その場では痛みがすぐにひき、普通に歩くことができてしまう。 倉本先生の指示により、松葉杖をやめ、正しいバランスで歩行し、患部を適度に冷やす日々を送る。それと、アルコールは禁止、とも言われてしまった。画期的なことに、お酒を11日間飲まなかった。これだけの期間飲まなかったのは、15年ぶりである。 腫れが再発せず、痛みが出なくなるまでには、それからさらに3週間ほどかかった。 8月に入ると、練習に復帰し、下半身の筋力トレーニングも再開することができた。 片足だけでなく、両足が使えない、恐ろしい状況を脱して、長い暗闇のトンネルから抜け出せたような気分である。冬が終わって春が来るように、雨が上がって晴れ間が出るように、夜が終わって朝日が昇るように、肉体が回復していく。地面を踏みしめながら、どれだけ天に感謝したことだろう。 先日の練習では、蹴りをアドバイスする際、お手本のつもりで人を蹴ってみた。バチン!という音が響く。何と心地良い手(足)応えか。この感触が、格闘技における醍醐味の一つだ。 翌日の筋肉痛が、また心地良い。自分がわずかずつでも成長しつつある実感が、久しぶりに甦った。それは無上の歓びである。「BUDO−RA」は今月号で終焉し、次回からは「格闘伝説」に変わる。月刊誌「BUDO−RA」は終わっても、私個人は武道・格闘技との関わりを、死が分かつまでやめられそうにない。 |
| ←前へ |
|
|